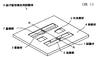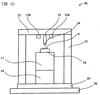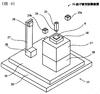| 出願番号 |
特願2007-000903 |
| 出願日 |
2007/1/9 |
| 出願人 |
国立大学法人名古屋大学 |
| 公開番号 |
特開2008-170160 |
| 公開日 |
2008/7/24 |
| 登録番号 |
特許第4501008号 |
| 特許権者 |
国立大学法人東海国立大学機構 |
| 発明の名称 |
曲げ疲労検出用試験体並びに曲げ疲労試験方法 |
| 技術分野 |
その他 |
| 機能 |
材料・素材の製造、検査・検出、機械・部品の製造 |
| 適用製品 |
曲げ疲労検出用試験体 |
| 目的 |
マイクロ材料の曲げ疲労試験における不確かさの要因となる位置合わせ等を必要としない、高精度で信頼性の高い曲げ疲労検出用試験体を提供する。さらに、この曲げ疲労検出用試験体を用いた、優れた試験方法を提供する。 |
| 効果 |
曲げ疲労検出用試験体を用いる場合、マイクロ材料の曲げ疲労試験において、微小な試験片を直接取り扱うことがなく、試験片の一定位置に正確に荷重を負荷させることができ、従来のマイクロ材料の曲げ疲労試験における不確かさの要因となる位置合わせ等が不要になる。この曲げ疲労検出用試験体を用いる曲げ疲労試験において、微小な試験片の位置合わせ作業が省略されるため、煩雑な手順が減り、作業能率を上げることができる。 |
技術概要
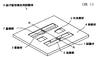 |
図1は、マイクロ材料の曲げ疲労検出用試験体の構成を示す斜視図であり、図2は、図1中の線分A−A’における断面図で、図2(a)は変形前、図2(b)は変形後の様子を表した図である。曲げ疲労検出用試験体6は、片持ち梁形状の試験片1と、試験片1を保持する中央部材2と、中央部材2に連結される梁部材3と、梁部材3に連結される枠部材4と、試験片1の先端側に位置する当接部5とを備える。図1と図2に示すように2本の試験片1を中央部材2の対称な2箇所に配置して対称形状とすることにより、一方が壊れるまで中央部材2は平衡が保たれた状態で移動する。そして、片持ち梁形状の試験片1の先端部を当接部5に対し当接させ、試験片1に曲げ変形を誘起させ、試験片1が曲げ状態となることで、疲労試験が行われる。図3は曲げ疲労試験装置の一部を正面から見た図、図4は曲げ疲労試験装置全体の斜視図である。図3、図4において、曲げ疲労試験装置50は、曲げ疲労検出用試験体6を固定するためのホルダ16を備える。 |
| イメージ図 |
|
| 実施実績 |
【無】 |
| 許諾実績 |
【無】 |
| 特許権譲渡 |
【否】
|
| 特許権実施許諾 |
【可】
|